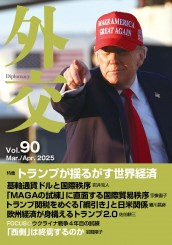基軸通貨ドルと国際秩序
世界の基軸通貨として流通するドル。
その影響力と強靭性を踏まえ、トランプの政策を捉え直す。
・基軸通貨の本質は、「みんなが使うから、みんなも使う」
・基軸通貨からの離脱や参入は極めて困難
・日本は、「西洋近代」にとどまらない普遍的価値の推進を
岩井克人(神奈川大学)
「MAGAの試練」に直面する国際貿易秩序
トランプ政権は米国再興のため友好国とも対峙し国際秩序を揺るがす。
安定化に向けた重層的取り組みが急務だ。
・「貿易赤字は悪」「製造業は国内回帰」に強い思い
・中国の、WTOルールの抜け穴利用に厳しい目
・日本は米国の孤立を防ぐ協力と、CPTPPなどの強化を
宗像直子(東京大学)
トランプ関税をめぐる「綱引き」と日米関係
第二期政権の関税政策は二派に分かれ、いずれも短期的成果を追求する。
世界各国や日本への影響は、対応は。
・政策の整合性はないが、中間選挙をにらんだ成果を急ぐ
・日本は自動車関税で日米貿易協定の有効性が問われる
・WTOなど「ルール遵守」各国協調のイニシアティブを
細川昌彦(明星大学)
米国中間層はトランプ関税で救われない
高関税を「強い国家主義の発動」として中間層の「怒り」を代弁。
だが経済の不安定化リスクは確実に増大する。
・「最初の一撃」をいろいろな国に対して展開
・高関税は「脅しの武器」だが、実際に使われることも
・保護主義の弊害の犠牲になるのは結局消費者だ
大越匡洋(日本経済新聞)
消費主導への転換図る中国経済
不動産不況、消費マインド低下、米中対立の三重苦にあえぐ中国経済。
全人代で示された再浮上へのシナリオとは。
・最重要課題は内需の拡大、財政政策も一段と積極化
・多国間経済協力を推進も、トランプ関税の逆風
・個人消費拡大を阻む少子高齢化と不十分な社会保障
伊藤信悟(国際経済研究所)
メキシコが蒙る「25%関税」のインパクト
NAFTA発効以来、米国との緊密化著しいメキシコ経済。
トランプ政権の不安定な関税政策が与える影響は。
・自動車産業の急成長が米国依存の貿易構造を加速
・日系企業の存在感は大きいが、中国からの部品輸入も増加
・25%関税に続く貿易協定改訂交渉も今後の鍵に
星野妙子(ジェトロ・アジア経済研究所)
トランプ2・0が及ぼすASEANへの影響
自由貿易体制の恩恵を享け、経済発展してきたASEAN。
保護主義・米中対立が加速するトランプ2・0の影響は。
・ASEANは世界の貿易投資拡大の中で経済が発展
・米中対立の「漁夫の利」による成長は困難か
・世界経済の低迷が影響するか。日本は連携強化を
清水一史(九州大学)
欧州経済が身構えるトランプ2・0
揺さぶられる欧州。中国・米国との関係とEUの競争力
強化政策はいかに。EU本拠のブリュッセルから俯瞰する。
・「グリーンディール」から「競争力ディール」への転換
・着実に進む欧州の経済安全保障政策にも米欧対立が影響
・米欧の不信の連鎖に対して、国際秩序の安定確保は急務
佐伯耕三(経済産業省)
若い大陸とどう関わるか――第九回アフリカ開発会議への戦略
USAID解体など、厳しさを増す国際開発援助体制。
TICADは新たなアイディアを示せるか。
・「若者×スタートアップ」に焦点を当て、積極支援
・「脆弱な雇用」からの脱却、スタートアップ頼みには限界
・産業構造の転換には産業政策的手法も有効
福西隆弘(ジェトロ・アジア経済研究所)
FOCUS◎ウクライナ戦争4年目の試練
「西側」は終焉するのか
当事者の頭越しに停戦交渉を進めるトランプ政権。
価値と政策を共有できない米国に欧州の苛立ちは募る。
・自立化の道を歩む欧州、兵器体系の見直しも
・ドイツは軍拡とインフラ整備を両立できるか
・他の同盟国にも懸念広がる。核拡散の可能性も
岩間陽子(政策研究大学院大学)
「停戦」を急ぐトランプ外交の論理
トランプ大統領が進めるウクライナ「停戦」。
ロシア寄りの姿勢は、国際社会を動揺させている。
・背景にはアメリカ第一主義と対中外交へのリソース集中
・対ロ交渉で重要な役割を果たす腹心ウィトコフ
・対中外交はラトニック、ウォルツが主導か
秋元諭宏(米国笹川平和財団)
変容するNATO 自立への苦悩と覚醒
ロシアのウクライナ侵攻とトランプ・ショックで
岐路に立つNATO。次代に向けた模索が始まっている。
・ウクライナNATO加盟、米独は慎重姿勢
・欧州の自立化進むも、米国の存在は不可欠
・巨大な脅威と内向きの米国、重なる日欧の戦略的課題
合六強(二松学舎大学)
インドネシアから見たウクライナとガザ
積極外交で国益重視と地域のリーダーシップ強化を狙う
プラボウォ外交の原点を探り、強みと弱みを分析する。
・ウクライナ戦争では食糧問題に注目。経済外交を進める
・ガザへの人道支援にイスラム代表として名乗りを
・外交の脆弱性が懸念される南シナ海・中国との経済協力
本名純(立命館大学)
対ロシア制裁と迂回輸出
経済制裁をかいくぐる迂回輸出が横行する。その摘発と
貿易管理レベルの向上が、国際社会の喫緊の課題だ。
・迂回輸出かどうかは時間を経ないと判定は難しい
・摘発と迂回輸出を狙う勢力とのいたちごっこが続く
・届出・許可を義務付けたキャッチオール規制にも限界
小野純子(外務省)
TREND2025
日米首脳会談「成功」後も続く試練
初めての石破・トランプ会談は大過なく終わった。
しかし会談の真の評価は、今後の懸案処理に委ねられる。
・首相はトランプ大統領と蜜月だった安倍氏のスタイルを継承
・USスチール、関税、防衛費、LNG開発… …懸案は山積
・トランプ政権を注視しつつ、トランプ後も見据えた外交を
今井隆(読売新聞)
韓国大統領弾劾と「分断」のゆくえ
身をもって感じた「非常戒厳」の緊迫。社会が分断されるなか、
尹大統領の弾劾は、次期大統領はどうなるのか。
・弾劾裁判は大統領の「職務権限」めぐり真っ向対立
・次期大統領に有力視される李在明氏の「リスク」とは
・韓国社会の政治的分断は克服されるのか
大谷暁(NHK)
ドイツ総選挙・苦悩するメルツ新政権
右派・極右・左派政党に議席が分かれ、国家大方針の基本法改正が困難に。
財政規律と安全保障の舵取りはいかに。
・戦後続いたドイツ政治のコンセンサスは終焉か
・防衛費のみならず経済の減速が財政規律遵守を困難に
・EUも変容するなか、新政権はドイツを安定化できるか
森井裕一(東京大学)
シリア新政権の試練 国民との「ハネムーンの終わり」
新政権発足一〇〇日を経て、治安機関への攻撃や政権支持者による
住民殺害が顕在化。国民統合の困難が浮き彫りに。
・国民の歓喜に迎えられた新政権は、内外の挑戦に直面
・新政権は民族、宗教、宗派の違いや
外国勢力による国土の分断を乗り越えられるか
・内外の分断と亀裂が続けば復興への悪影響も懸念される
松本太(日本国際問題研究所)
アメリカの州政府に広がるイスラエル支援
米国の対イスラエル支援は連邦政府のみならず、
国債の購入を通じて、一部の州政府も積極的役割を担う。
・戦争当事国への直接的戦費供与という特殊な性格
・政治的動機を背景に投資を主導する共和党系財務責任者
・保守系団体を通じイスラエルと州・地方政府との財政的連携進む
梅川葉菜(駒澤大学)
「ルワンダ問題」としてのコンゴ東部紛争
コンゴ民主共和国東部に起こった武装勢力による制圧劇。
背景には隣国ルワンダによる長い「干渉」の経緯がある。
・同地域には歴史的にルワンダ系住民が数多く流入・定着
・豊かな鉱物資源の一部は密輸によりルワンダ側の利益に
・コンゴは国際社会の介入に頼るが、奏功していない
華井和代(東京大学)
フィリピン・ミンダナオ 新自治政府成立に向けた選挙の行方
自治政府設立のための選挙を一〇月に控えるミンダナオ。
半世紀に及ぶ対立と不信の歴史を克服できるか。
・恩顧主義が根付く地で、複雑な政治的駆け引きが展開
・最大の争点は暫定自治政府を主導するMILFへの評価
・選挙の実施に向けて、自治地域の治安悪化は懸念材料
谷口美代子(宮崎公立大学)
ドゥテルテ逮捕に揺れるフィリピン政治
人道に対する罪への疑いで逮捕された前大統領。
現在も比国内で一定の影響力を持つだけに、その衝撃は大きい。
・「大量虐殺者」か「庶民の英雄」か、割れるドゥテルテ評
・国内政局は「マルコス家対ドゥテルテ家」の対立が軸に
・支持者の間には「ドゥテルテ=殉教者」への共感が高まる
日下渉(東京外国語大学)
注目集めるグリーンランド自治議会選挙
トランプ大統領の「領有」発言や漁業問題など
多岐にわたる論点で争われた三月一一日の自治議会選。
・選挙結果は、左派優位の歴史を覆す右派政党の勝利
・水産業における規制強化の是非が主要な争点
・独立論と対米重視論が交錯すると大きな政治変動に
高橋美野梨(北海学園大学)
連載
外務省だより
Information
Book Review
安保改定と政党政治ーー岸信介と「独立の完成」
高橋和宏(法政大学)
新刊案内
英文目次
編集後記
IN&OUT